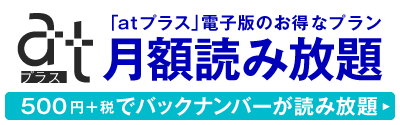ぽっかり浮かぶ「資本主義の小島」の魅力
――星野さんは作家としてのデビュー作『謝々!チャイニーズ』と写真家としてのデビュー作『華南体感』から、『転がる香港に苔は生えない』まで、激動する中国や香港で生活しながらその地の息吹をいきいきと伝えています。どのような経緯で中国や香港に興味を持ったのでしょうか。
星野 もともと中国やソ連といった社会主義国家に興味があり、学生時代に旅行していました。中国のトップは胡耀邦(1915-1989、初代中国共産党中央委員会総書記)で、ソ連はユーリ・アンドロポフ(1914‐1984、ソビエト連邦第六代最高指導者)が死去し、ゴルバチョフが書記長になったばかりの時代です。両者とも従来の社会主義国家から民主化を進めようとした人物です。もっとも、当時はそんなことは露ほども意識していませんでしたが。
旅するなかで特に気に入ったのが、ベルリンでした。もちろんベルリンの壁が存在していた頃の話。東ドイツという社会主義国家の海の中にぽっかり浮かぶ、「資本主義の小島」のような街です。
ドイツの首都として君臨するいまのベルリンからは想像もつきませんが、当時の西ベルリンは、東ドイツから亡命した人と、徴兵を拒否して西ドイツから逃げてくる若者のたまり場で、アナーキーな空気が支配していました。東ドイツ国内にぽかんとある街なので、そこを再開発しようとする人なんて誰もいないからすごく物価が安くて、空き地だらけで、パンクが勝手に古くなった建物を占拠したり、自由な芸術活動が行われたり、とっても刺激的な街だったんです。
それで西ベルリンから電車に15分くらい乗って東ベルリンに到着すると、一瞬にして社会主義建築や労働者のモニュメントが建ち並ぶ社会主義国家の風景になる。電車で資本主義と社会主義を行ったり来たり。社会主義的風景好きの自分にはたまらない体験でした。日本という島国ではなかなか体感できない「国境」を、東西ベルリンで意識するようになりました。
私の中国好きは幼少期からの癖のようなものなんですけど、西と東の狭間に浮かぶ小島・西ベルリンを体験したことで、興味の焦点が次第に中国から香港へ向くようになりました。香港は阿片戦争(1840‐1842)の戦利品としてイギリスに奪われた植民地ですが、中国の共産化を嫌って亡命してきた人たちが住民の多くを占めている。亡命者が多い社会主義国家の中に浮かぶ小島のような場所、という点が、西ベルリンと重なって見えたんです。そして香港に留学したのが1986年のことです。私は「香港の星野」みたいに呼ばれることがあるのですが、実はその原点はベルリンだったんです。
――作家という職業を意識したのはいつですか?
星野 漠然と、何か書いてみたいなあと思い始めたのは香港に留学していた頃。私は2008年に、1987年の中国を描いた『愚か者、中国をゆく』という本を出しましたが、ベースになったのは学生時代に書きなぐった原稿です。あの原稿が世に出せたときは本当に嬉しかった。でも当時はどうしたら本を出せるかわからず、いきなりそんな世界に飛び込む勇気も気概も持てず、大学卒業後は一般企業に就職しました。でも会社生活は1年ともたず、88年の暮れには辞めてしまいました。ちょうどその頃、香港映画をテーマにした映画祭が渋谷で開かれることになって、少しの間、その手伝いなんかをしていました。『男たちの挽歌』(1987年制作の香港映画。監督はジョン・ウー)で一躍日本でもその名が知られるようになった香港のトップスター、周潤發(チョウ・ユンファ。1955‐)が公式初来日したとき、通訳をさせてもらったのは私! 数少ない、私の自慢です。
そして因縁の1989年がやって来ます。民主化を進めて失脚した胡耀邦の死を引き金に、中国では6月4日に天安門事件が起き、一方ミハイル・ゴルバチョフの進めたペレストロイカが東欧全域に波及して民主化を要求する声が高まり、11月にはとうとうベルリンの壁が崩壊しました。
この先どうしようと悶々としていた矢先に、世界が大激変したことは、いま思えば自分にとって大きな後押しになったような気がします。変わりゆく世界を理解したい。そんな仕事をしたい。「ぼんやりと」から、少しはっきり、そう思うようになりました。
もっとも、そこにはバブル世代特有の、どうしようもない楽観性のようなものもあって、「先は見えないけど、ま、なんとかなるさ」みたいな軽いノリでした。いまでもそんな感じです。行き当たりばったり。あまり先のことは考えていない。
文章脳と写真脳
――デビュー当時は写真集も出されていて、作家と写真家という二足のわらじで活躍されていましたが、最新作『みんな彗星を見ていた』をふくめ、最近のお仕事は文章だけということが多いです。写真から文章へと、表現方法がシフトしているのでしょうか。
星野 たまたま写真と文章というセットでデビューしているので、写真人間かと思われがちですが、実は全然写真人間ではないんです。最初から、やりたいのは文章を書くことだった。もともと写真から出発した人間ではないですし、今回の本でも必要ないと思ったので、写真はスペインに行ったときにちょっと撮ったくらいで、ほとんど撮っていません。
写真をやるときと文章をやるときでは使う脳みそが違うので、二つの行為はなかなか同居できないんです。写真と文章では、歩き方が全然違います。たとえば写真を撮るときは博物館とかには絶対に行かないし、人に聞く話も違ってきます。とにかく朝どこから太陽が出て、このあたりがきっといい夕日になりそうだな、なんて考えながらずっと待っているとか、そういう思考回路になっていきます。極力、頭は使わない。一方、何かを書きたいときには頭がフル回転になるので、朝日や夕日をじっくり待ったり、よい風景を探して歩くことができなくなる。
いい写真には言葉は必要ないし、書きたいことが山ほどあるときに写真は必要ない。若い頃は体力があり余っていたのでなんとか両方やっていましたが、この二つを同居させようとすると、必ず無理な力がかかるので、いまはあまりよくばらないようにしています。「あれ、カメラどこにしまったっけ?」となるくらいです(笑)。スペインに行くときにカメラを準備していて、あまりに久しぶりだったのでASA感度(光に対するフィルムの能力を示す値)の設定の仕方を忘れ、マジで青ざめました。
とはいえ、写真の経験は知らず知らずのうちに現場で役立っています。知らない場所でいきなり人に近寄って「話を聞かせてください」と頼んで、その一瞬で「こいつには話してもいい」と思ってもらうにはどうしたらいいか。説明が難しいのですが、「私、敵ではありません」オーラと「あなたに興味あります」オーラを出すこと(笑)。
ある町や村へ行き、どこへ行けば人と会えそうか。誰が進んで話をしてくれそうか。どの人を信用すればよいか。場の気配を感じとったり、人の波長をつかんだりすること。それらはみな、カメラを通して培ったように思います。猫のヒゲのようなものですね。
キリシタン弾圧と日本人
――中国や香港をテーマにした著作につづいて執筆された『コンニャク屋漂流記』では、一族の故郷である外房の岩和田を舞台に、紀州の漁師であった先祖がなぜ岩和田に来て、一族がどのように暮らしていたのかを驚くべき取材力で明らかにされました。
今回書かれた『みんな彗星を見ていた』では、戦国時代に始まるカトリック宣教師たちによる日本布教からキリシタン弾圧にいたるまでの歴史を、将軍や大名、神父、民衆など、さまざまな立場の人々に光を当てながら紐解いています。特に、大航海時代まっただ中で、家康統治下の400年前に焦点が当てられていますが、なぜこの時代、このテーマだったのでしょうか?
星野 キリシタン弾圧のことはずっと長い間引っかかっていて、いまの私たちの暮らしや考え方に確実に影響を及ぼしているのに、直視されていないという思いを抱えていました。なぜ日本人が熱しやすく冷めやすかったり、何かを系統立てて理論的に考えたりしないのか。振り子が触れるように、一方から一方へなだれこむ傾向があるのはなぜか。人目を気にし、出る杭となることを恐怖すること。自主性より全体を重んじる傾向。忘れっぽさ。西洋に対するねじれた羨望と、東洋に対する優越感。結婚式はキリスト教で、死ぬときは仏教、というように、宗教に寛容なのではなく、無節操になったのはなぜか――そういった諸々の日常的なこともふくめて、400年前のキリシタンの時代が関係あるのでは?という漠然とした考えがあったんです。
間接的なきっかけとなったのが、『コンニャク屋漂流記』でした。これは外房・岩和田の鰯網の漁師だった自分の先祖が、どのような道のりを経て生きてきたかをつづったノンフィクションなのですが、一族の歴史を調べるうちに四世紀前を身近に感じられるようになりました。400年前は意外と古くない過去で、自分もそこにアクセスする権利がある、と思えたことは大きかった。いまでは、1700年代でさえ、「わりと最近だな」と思う(笑)。
またこの作品を通して、一族の長老から「ドン・ロドリゴ」の話を聞いたことも、大きな刺激になりました(ロドリゴ・デ・ビベロ、スペインの植民地政治家。1564‐1636)。ドン・ロドリゴはフィリピン臨時総督で、1609年にマニラからアカプルコを目指して航海中に岩和田の浜で遭難しました。56名が溺死し、残りの317名が岩和田の住民たちに助けられたのですが、瀕死の異国人を裸になって温めたという話が一族の中に生きていたことは本当に驚きでした。四世紀前に自分の先祖と大航海時代のスペインが束の間の接触をした! この思いこみは、数年にわたってキリシタンの足跡を追いかける際のガソリンになりました。
前からキリシタンに興味があったとはいえ、まだ全然知識もないときに、岩和田でドン・ロドリゴの話を聞いて「なんでスペイン船がここで座礁したのだろう?」と疑問に思い、そうするうちにスペインとポルトガルの対立が見えてきて、「おや、実はこの時代のことを全然知らないのでは?」と痛感したことが、『みんな彗星を見ていた』の通奏低音になっています。あの村でドン・ロドリゴが遭難していなければ、それほどこの時代に留意することはなかったと思います。
今回本を書き上げることで、いまの日本人が当然と思いこんでいるようなものの考え方は、キリシタン弾圧と関係しているという思いはさらに強まりました。
――具体的にはどのような点でしょうか?
星野 キリスト教は、1549年にフランシスコ・ザビエルによって日本にもたらされ、一時期厚遇されますが、その後苛烈な弾圧を受けます。キリシタンと外国人宣教師が大量に殺され、1637年から1638年にかけて島原の乱が起こる。その結果、17世紀に入って寺請制度という、すべての人民は寺に所属するというシステムが作られたり、キリシタン類族帳というものができ、疑わしい人間について男性は六代、女性は三代先まで監視されるという、キリシタン弾圧のシステムが末端まで作り上げられました。これにより、周囲を隣同士で監視しあうという体制を長い時間をかけて作り上げたので、相互監視システムが構築されやすかったのではないかと思います。ベースがすでにあるので、隣同士で監視しあって「あいつは非国民だ」と告げ口させるようなことがすぐにできる。それは確実にいまの私たちにも影響していると思います。
キリシタン史には穴がある
――クリスチャンではない星野さんが、ここまで徹底的にキリシタンの歴史を調査されたことに驚きました。
星野 クリスチャンでないからこそ、かもしれません。信仰心があったら、調査したいとは思わなかったのではないでしょうか。
それに、別にたいした調査をしたとは思っていません。たとえば、ローマのイエズス会古文書館に通いつめて、原語で一次史料にあたるほどのことをしていれば、多少は評価できるかもしれませんが、私の場合、日本語に訳され市販された史料を使ったわけですし、さほどの苦労はしてない。逆に、海外渡航がたやすくなかった時代に一次史料を現地で採集し、研究し続けてきたキリシタン史の研究者に感謝したい思いでいっぱいです。そういう方々の情熱のおかげで、私もこの時代にアクセスすることができたわけですから。
ただ資料を読み進めるなかで、キリシタン史には穴があるように感じたのは事実です。キリシタン史にはどうしても、宗教がからんでくる。研究者にも宗教関係筋の方と東西交渉史畑の方がいて、布教のポジティブな影響を強調する方もいれば、カトリックの世界戦略をクローズアップする方もいる。その間を埋め、自分は立ち位置をどこにすればいいのか。深い森に迷いこんだような気持ちになることがしばしばありました。
そんななか自分がたどり着いた一つのスタンスは、当時生きた人間の心性を、できる限り自分にたぐり寄せて想像してみる、ということ。スペインやポルトガルといった国家を背負い、神に生涯を捧げた宣教師といえども、冒険心に満ちたひとりの人間だったはずです。この人とは友達になれそうにないが、この人とは友達になれそうだ。この人は性格悪そうだけど、この人はとっても穏やか。グルメな神父と修行命の神父がケンカをしているぞ! そんなことに注目しながら資料を読み始めたら、すっと心に入ってくる瞬間があったんです。そのあたりから、ぐっと彼らを身近に感じるようになりました。
宣教師たちの「マーケティング」
――宣教師たちが危険を冒して海を渡り、まったく違う言語をマスターして、布教のための方策を練り上げてアジアに進出してきたことの背景には、ヨーロッパでカトリック以外のものの脅威が迫っていたということが関係しているのでしょうか。
星野 脅威というより、自ら作り出した危機感だと思います。宗教改革が起こるわ、イギリスはローマ教皇の支配から逃れるためにイギリス国教会を作るわで、ヨーロッパにおけるローマ・カトリックの威信は低下する一方。ヨーロッパ以外の場所へ活路を見いだす機運は高まっていたと思います。なかでもイエズス会は「イエスのための軍隊」という性格を持ち、海外布教を念頭に置いて作られた修道会なので、特に力が入っていた。
ご存じの通り、日本に最初にキリスト教を伝えたのはイエズス会のフランシスコ・ザビエルでした。イエズス会はポルトガル王室と結びつき、ポルトガルの行くところへセットでやって来ます。日本でも最初の30年あまりはイエズス会が布教を独占していました。天正遣欧少年使節はローマへ向けて1582年に船出をしますが、このころがキリシタンにとっては、最も平和で繁栄した時期だったと思います。
ところが使節がマカオに到着すると、ポルトガルを治めていたエンリケ卿が死に、世継ぎがいなかったため、スペイン国王フェリペ二世がポルトガル王位を継承したというニュースがもたらされます。日本の民やキリシタンにはまったく関係ない異国の話ですが、イエズス会にとっては大変な衝撃です。言葉は悪いけれど、自分たちがゼロから耕し、ようやく実りの時期を迎えていた日本という市場が、スペインに開放されてしまうからです。
秀吉の時代に入ると、案の定、新大陸とフィリピン経由でスペイン系修道会の神父たちがやって来るようになります。フランシスコ会、ドミニコ会、アウグスチノ会という、ヨーロッパでは長い歴史を持つ托鉢修道会です。当然ながら、先発部隊であるイエズス会は脅威を感じ、行く先々でテリトリー争いのようなことが起こり始めます。
この点は中国と比較をすると興味深いところなんですが、中国でもイエズス会が強かったとはいえ、中国はあれだけ広いので、イエズス会は皇帝のおわします北京、ドミニコ会は南の福建、フランシスコ会は東北方面というように、ある程度の住み分けができたんですね。ところが日本ではそれもできなかった。唯一フランシスコ会は、イエズス会の強い地域から離れて東へ向かい、住み分けをしようとしますが、迫害の激化によって不可能になった。
――日本では、民衆への布教はどういうルートで進んだのでしょう。

- アレッサンドロ・ヴァリニャーノ

- マテオ・リッチ
星野 イエズス会は「上から布教」が最も効率がいいと考えました。まずは上を改宗させ、そうしたら領民を全員改宗させていき、どんどんテリトリーを広げていく。日本でも中国でも、この方針が採られました。
その基本路線を敷いたのはアレッサンドロ・ヴァリニャーノというイエズス会巡察使。ヴァリニャーノは日本布教がうまくいっていないらしいと聞いて視察に来て、日本がどのような社会かを見抜き、上から布教を徹底させようとしました。彼の見立てでは、修道士たちは日本の仏僧のような格好をして、物静かで、頭がよく見えるように振る舞って、まず尊敬を勝ち取らなければいけない。日本人というのは、尊敬しないかぎりは絶対に受け入れないということを瞬時に察知したわけです。
ヴァリニャーノは、日本人から野蛮人と思われないよう振る舞うにはどうすべきか、という『日本イエズス会士礼法指針』を書くんですが、これがまるで「日本駐在外国人ビジネスマン必携マナーガイド」みたいでおもしろいんです。急いで歩くな、笑いすぎるな、釣りをしようとして川へ向かって走ってはならない、きょろきょろするな、贈り物は欠かすな、手足をバタバタ動かすな、といった具合で、読んでいて笑ってしまいます。当時の日本人は無条件に南蛮人に憧れたり、ひれ伏したりしていたわけではないことがわかって新鮮でした。
――中国での布教は様子が違ったのでしょうか?
星野 中国では、パイオニアとしてマテオ・リッチが最も有名ですが、彼もヴァリニャーノの弟子ではあります。リッチたちもヴァリニャーノ式を踏襲して、この社会に入っていくにはどういうシステムを作ったらいいかをじーっと考えたわけです。そして最初は中国でも日本方式で仏僧の格好をして尊敬を勝ち取ろうとしたのですが、石を投げられて蔑まれ、どうも勝手が違う。そしてそのとき初めて、中国では仏教では駄目なんだと気づきます。当時の中国では、仏僧は物ごいのような扱いを受け、一番尊敬されるのは儒学者なんですね。そして「間違えた!」と袈裟を脱ぎ、儒学者の装束を着て習字などをしていたら、ようやく尊敬されるようになります。
――キリスト教が受け入れられやすいようにパッケージングするという、いまのマーケティングの考え方に近いことをやっていたのですね。
星野 そうなんです。イエズス会の東方布教のやり方が、現代のマーケティングの元祖なのでは、と思ってしまうくらいです。
儒学者の格好をして、そうこうするうち「そのほう、天文学に詳しいらしいな」と皇帝からお声がかかります。ヴァリニャーノが日本で贈り物を重視した話はさきほど触れましたが、中国で贈り物として人気があったのは時計です。中国は、皇帝がトップに君臨し、科挙に合格した秀才を全国に知事として派遣するという統治システムなのです。皇帝がいて秀才の集結する北京を、イエズス会は最重要布教地と考えました。南蛮船の来る九州を中心にせざるを得なかった日本とは、その点も大きな違いです。そして神父たちは、皇帝の周囲の要人たちに時計を贈るんです。世界最先端のからくり時計みたいなものを。学生のころ、北京の故宮(博物院)でそうした時計をたくさん見たことがあって、なんで中国にはこんなに時計があるのかと不思議に思っていたのですが、イエズス会が広めたんですね。目からウロコでした!
しかし時計は定期的にメンテナンスをしないと、いずれ必ず止まることになっている。イエズス会士でなければ時計を動かすことはできません。「時計を直しに来てくれ!」と方々から要請が来ます。するとイエズス会の修道士は貴人の家まで入ることができるわけです。そして時計をいじりながら、「チョットイイデスカ?」と話を始める。分厚い扉を開けて中へ入るにはどうしたらいいのか、それを計算したうえでの時計だった。なかなかやり手です。訪問販売の元祖みたい。こういう話は大好きです。
私は中国や香港に縁があるので、キリスト教布教の歴史にしても、どうしても日本と中国を比較してしまうのですが、興味は尽きません。中国でもゆくゆくキリスト教は弾圧されるんですが、もともとあれだけの長い歴史と広大な版図を持った多民族・多宗教国家なので、辺境へ追放すれば見逃すといった逃げ道がある。ムスリムもユダヤ人も景教徒(ネストリウス派キリスト教)も古くから入っていて、多様性においては懐の深さのレベルがまったく違います。だいたい、明朝の永楽帝の命で船団を率いて東アフリカまで到達した鄭和(1371‐1434)はムスリムの宦官ですからね。モンゴル族の元朝はいうまでもなく、明朝を倒した清朝も、満洲族の異民族王朝ですし。私たちがイメージするよりもはるかに多様性のある場所、それが中国です。それを一つの国にまとめるにあたり、はじめて一色で統一したのが共産主義。その中国が、体制を守るため、いまはウィグルのムスリムやクリスチャンやチベット族を弾圧している。中国が長い歴史の中で培ってきた多様性という宝物を、自ら手放す行為に私には映りますね。
――星野さんの本を読み、お話を聞いていると、私たちが想像する「布教」や「宣教師」のイメージからは大きくはみでるような人間臭いエピソードが満載で、つい400年前の話であることを忘れてしまいそうです。
星野 この時代の話を、布教の歴史だと思うとどうしても距離が縮まらない。でも現代に通じる部分を探していると、どこかに必ず自分との接点が見つかるんです。すると神父やキリシタンが同じ地平上の人間だと思える瞬間がある。
たとえば当時、航海途中に別の職業から修道士へ鞍替えした人は少なからずいるんです。インド貿易で荒稼ぎして、日本にも稼ぎにこようと思ったポルトガル人がたまたま神父と同じ船になり、航海中にひどい嵐に遭って、「生きて日本に着けたら神父様に命を捧げます」なんて言ったり。大分に日本で初めての病院を建て、初期の布教に尽力したルイス・デ・アルメイダ(1525‐1583)はこのケース。ザビエルの右腕コスメ・デ・トーレス(1510‐1570)は、「自分探し」みたいなノリでスペイン艦隊に乗りこんで香料諸島でポルトガルの捕虜になり、ザビエルに出会ったことで一生を共にすることを決心します。
もちろん逆のケースもあって、貿易商人から修道士に鞍替えして日本に来たものの、「やっぱりムリ!」って逃げた人もいます。「俺、本書くわ」と言って作家になったのが『東洋遍歴記』のメンデス・ピント(1509‐1583)。そういうくだりを読むと、人間臭くて嬉しくなります。現代の「自分探し」と似ているんですよね。船で旅して知らない世界へ行くというのは、当時最先端の冒険だったので、それが神に向かうのか、自己実現のほうに向かうのかという違いでしかない。そう考えていくと、当時の宣教師も未知の人間じゃなくて、自分たちと同じような人間臭さを持っているんだな、と思うようになりました。
いまそこにある弾圧
星野 1614年に神父たちが国外追放される時点で14もの教会があった長崎は、信仰を理由に故郷を追われたキリシタンが集まる場所でした。富と亡命者が集まってできた香港みたいなものです。そしてキリシタンは、自分の考えでイエズス会の教会へ行ったり、ドミニコ会の教会へ行ったりしていました。長崎は教会の集結するショールームみたいな場所。信徒の舌も、他の土地よりずっと肥えています。神父たちにとっては、あなどれない場所だったはずです。
長崎では、修道会同士、信徒同士の対立や勢力争いも起きました。そんな話が資料を読んでいるといくらでも出てきます。人の心を救済するはずの神父が何をやっていたのだ、とため息が出ることもありましたが、そういう部分に惹かれる自分がいたのも事実。自分たちと何ひとつ変わらないじゃないか、と思えば思うほど、彼らがリアルに感じられるようになった。
――日本のキリシタンは、会派による教義の違いまでわかっていたのでしょうか?
星野 個々の信徒がどういう考えで、通う教会や従う神父を決めていたのかはわかりません。ただ少なくとも、自主性は明確に持っていたと私は思っています。自分に置き換えて想像してみたらわかりやすいのですが、豪華絢爛な教会に惹かれる人もいたでしょうし、質素な教会でないと信じられない、という感性を持つ人もいたかもしれない。神父の人柄で選ぶ人もいたでしょうし、教義の違いを明確に認識して選ぶ人もいたでしょう。
「うちの神父様はこう言っているけど、向こうの神父様はこう言っている。どうしたらいいのか」といった問題は頻繁にあったようで、神父の書簡にもたびたび登場します。こういう苦悩が信徒から上がり、信徒の間で対立が起こったこと自体、教義の違いを彼らが認識していた証しといえるのではないでしょうか。
質問の答えになっているかどうかわかりませんが、当時のキリシタンの様子を描写したもので深く印象に残っているくだりがあります。ドミニコ会のハシント・オルファネール神父(1578‐1622)が手紙にこう書いています。
「彼らは立派な死を迎えるように特に注意し、誰かが死んだということを聞くと、立派な死を迎えたか、と訊ねます」「キリシタンが深い信心を抱いて私たちを迎えるために生命を危険に晒し、或る所では焼き殺される危険があるのに私たちを迎えてくれるのを見るとき、私たち修道士が彼らの模範とならずにいられるでしょうか? またこのキリシタンたちを尊敬せずにいられるでしょうか?」(『福者ハシント・オルファネールO.P.書簡・報告』より)
キリスト教の弾圧は、初期は領外追放や俸禄召し上げなどから始まり、キリシタン大名や多くの信徒が脱落しました。ところがけっして棄教しない人たちがいる。迫害が進行するにつれ、信仰の維持はほぼ、死に直結しました。生きるための信仰から、死ぬための信仰になってしまったんです。
どこかで殉教が起きる。その不屈さと不従順を、体制側は不気味で危険な存在と恐怖するようになります。恐怖するからこそ迫害の手段は残酷化してゆき、さらに殉教が起きる。信仰の観点から見れば自分には縁遠い話のように思えますが、「反体制」「反権力」と見なされた人たちに対する弾圧だと見れば、いつか自分たちにも起きるかもしれない話のように思える。それがキリシタン史のシンクロニシティだと私は思っています。
いまの世界を理解したい
――宗教が個人の救済である一方で、現代に至っても宗教を原因とする戦争やテロが各地で起きています。その矛盾について、この本を書き上げるなかで何か新しく見えてきたことがあれば教えていただけますか。
星野 西洋と東洋の歪んだ関係性に対する不満や怒りがマグマのように溜まった結果、世界のあちこちから清算を求める声として噴出している。私にはそう見えてなりません。大航海時代を皮切りに、西洋の価値観が力でその他の地域をねじ伏せ、世界の覇者として君臨してきた。それに対するリベンジではないか。
これをキリスト教世界とイスラームの対立といった構造に落としこむことは、むしろ避けるべきではないかと思います。それは構造を単純化するだけで、異教や異文化への不信や憎悪を煽ることにつながりかねない。長い年月を経てこじれた関係を修復するには、こんがらがった糸を一つずつ解いていく忍耐力が求められる。異なる他者とどれだけ忍耐を持って向き合えるか。大袈裟に言えば世界が大きな試練を与えられていると思います。
私は中学・高校とミッションスクールに通ったのですが、キリスト教を受け入れることはできませんでした。砂漠で誕生した宗教なのに、なぜ私が礼拝で目にするイエスやマリアの像は、明らかに西洋人の顔をしているの? 西洋絵画に描かれる聖書のシーンが、どう考えてもベツレヘムじゃなくてローマに見えるんだけど。キリスト教徒がユダヤ人を迫害したのはなぜ? そんな数々の疑問に立ち止まってしまい、その違和感を誰も説明してくれないんです。キリスト教には何か、積極的に説明しようとしないことが数多く隠されている! そう思ったら、キリスト教を単純に受け入れるわけにはいかなくなりました。いまは、ローマ化されたキリスト教が世界を席巻したからこそ、このようなパッケージで日本に伝わったのだということがわかりましたけど、それを理解するまでに途方もない時間がかかりました。
そんな不信心者ですが、それはたまたま自分が平和な国で平和な時代に生まれてそれほど不正義の犠牲とならず、幸い健康にも恵まれていたから宗教に惹かれなかったのであって、病気やいちじるしい不正義に見舞われたとき、何かの宗教にすがりつくかもしれない。さきほど、日本のキリシタンが死ぬために信仰を強固にしていったことに触れましたが、死への恐怖や不正義、死が近いという予感は、宗教の最大の磁力の一つだと思うんです。
だからこそ、戦争やテロで犠牲になる人が増えれば増えるほど、宗教対立、民族対立が深まることにつながりかねない。その悪循環がいま世界で加速している。答えは簡単には見つからない。それでも立ち止まって考え続けなければならない。
「テロ」という言葉も、語源は恐怖。他者に恐怖を与えて積年の鬱屈を晴らす行為には共感しませんが、そこまで彼らをかきたてる「積年」は理解したい。自分はその一歩から始めたいと思っています。
たまたま今回は400年前の日本におけるキリスト教をテーマにしましたが、その世界を肌身で感じたことで、現代を考えるヒントが過去にはたくさん眠っていると思うようになりました。いまの世界をより理解するために、過去を知りたいんです。すごく遠回りかもしれないし、どこへ行き着くかもわからないけど、どこか陸地にたどり着くことを願って舟をこぎ続けたいですね。